「心配事は無い」なんていう人はいません。
生きていれば常に心配や不安が湧いて出てきます。
不安の原因となるのは、命を脅かされるような危険に対する防御反応なので、誰にも持ちあわせているあたりまえの本能です。
しかしその不安の多くは、目の前の出来事や未来に対して本能がつくり出すものです。
不安のほとんどは、自らがつくり出しているものといえます。
このような視点に立ってみると、不安が不安でなくなってきます。
むしろ不安があることで、最悪な状況を回避するための準備を万全にすることができることになるとも考えられます。
不安はついてまわるもので、切り離せる方法は無いと考えましょう。
不安に翻弄されることなく、不安と上手に付き合っていくことが大切なのではないでしょうか。
では、不安をどのように理解し、付き合っていけばいいのでしょうか。
その疑問に、書籍「心配事の9割は起こらない」をもとに、読み解いていきます。
枡野 俊明(ますの しゅんみょう、1953年2月28日 – )
日本の僧侶、作庭家。曹洞宗徳雄山建功寺住職、日本造園設計代表、多摩美術大学教授、ブリティッシュコロンビア大学特別教授(Adjunct Professor)。神奈川県横浜市生まれ。
(Wikipediaより)

「心配事の9割は起こらない」抜粋&レビュー
人間関係の悩みとは?
人に対する好ましくない感情やネガティブな評価の背景には、実は色眼鏡をかけた自分がいるのだということを知ってください
それを外したら、見え方はガラリと変わったものになるでしょう。
(本文中より)
人に対して、思い込みや決めつけで、判断はしていないでしょうか?
これまでの生き方が自分自身の価値観となり、先入観としても判断に影響しています。
価値観や先入観が「色眼鏡」といってもいいでしょう。
思い切ってその色眼鏡を外してみましょう。
光と影、磁石にプラスとマイナスがあるように、マイナス、影の面ばかりに目を向けているとプラス、光の面は目に入りません。
暗い方へ目を向けるよりも、明るい方へ目を向ける方が、人は本来好むはずです。
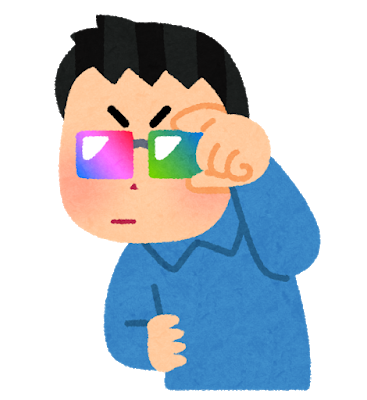
仕事を楽しくするには?
心から楽しめるものに打ち込んでいたら、その瞬間、瞬間を充実して生ききることができます。
心から迷いや不安が消えて、どんどん前向きになってきます。
(本文中より)
仕事は楽しいですか?
多くの人が、何らかの現状への不満、愚痴などが口をついて出るのではないでしょうか。
不平不満を言い訳にして、目の前のことをおざなりにしていませんか?
今ある仕事は、誰かの役に立ち、必要とされているからこそ存在しています。
不要ならば、当に消えて無くなっています。
当然、仕事には厳しい面があります。
そういった厳しさにのみ着眼している限り、仕事の本質は見えてはこないでしょう。
何がどうであれ、自分自身で選んだ仕事です。
誰かの役に立つからこそある仕事として考えてみると、その仕事の見え方も変わってくるのではないでしょうか。
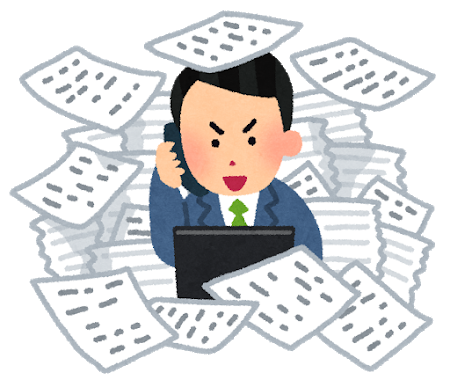
結果を出すコツとは?
自分のできる努力をコツコツ続ける習慣を身につける。
その「習慣」によって「才能」を超えることもできる。
(本文中より)
「習慣」という言葉を聞くと、この詩を思い出します。
「心」
心が変わると、態度が変わる。
態度が変わると、行動が変わる。
行動が変わると、習慣が変わる。
習慣が変わると、人生が変わる。
自分自身の生きる指標ともしている言葉です。
「歯みがき」をせずに一日を過ごすのは非常に気分の悪いものではないでしょうか。
それは、「歯みがき」が習慣となっているからです。
「歯みがき」が習慣となっているから、虫歯を予防することができています。
結果を出したいなら、何事も「習慣」と呼べるレベルまで、コツコツと継続することです。
「継続は力なり」とも言われますが、「習慣こそ力」ともなります。
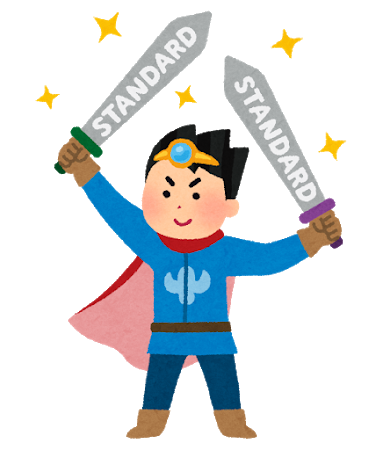
本書を読み終えて
新しい経験には新鮮な驚きや発見が得られるとともに、「不安」も付きまといます。
人は未知なもの、理解できないもには好奇心をかき立てられるとともに、不安をも抱く生き物です。
本書では、不安に対する考え方や心の持ち方を、著者の禅僧たる禅の精神の観点から学ぶことができます。
人は、我欲、承認欲求などの執着を持っています。
それらがあってこそ力強く生きていけるともいえます。
しかし、思いどうりにいかない現実においては、それらは不安の種となって自分自身を苦しめてしまいます。
本書内では、ポイントは、減らす、手放す、忘れる、とあります。
言い方を変えれば、執着を手放す生き方ともいえるのではないでしょうか。
今、目の前にあることに全力で取り組んでみましょう。
執着を手放し、シンプルな生き方をつらぬく人には不安など無いのかもしれません。
日々つきまとう、あなたの「不安」とは一体なんなのか?
本書でその答え探しをしてみてはいかがでしょうか。
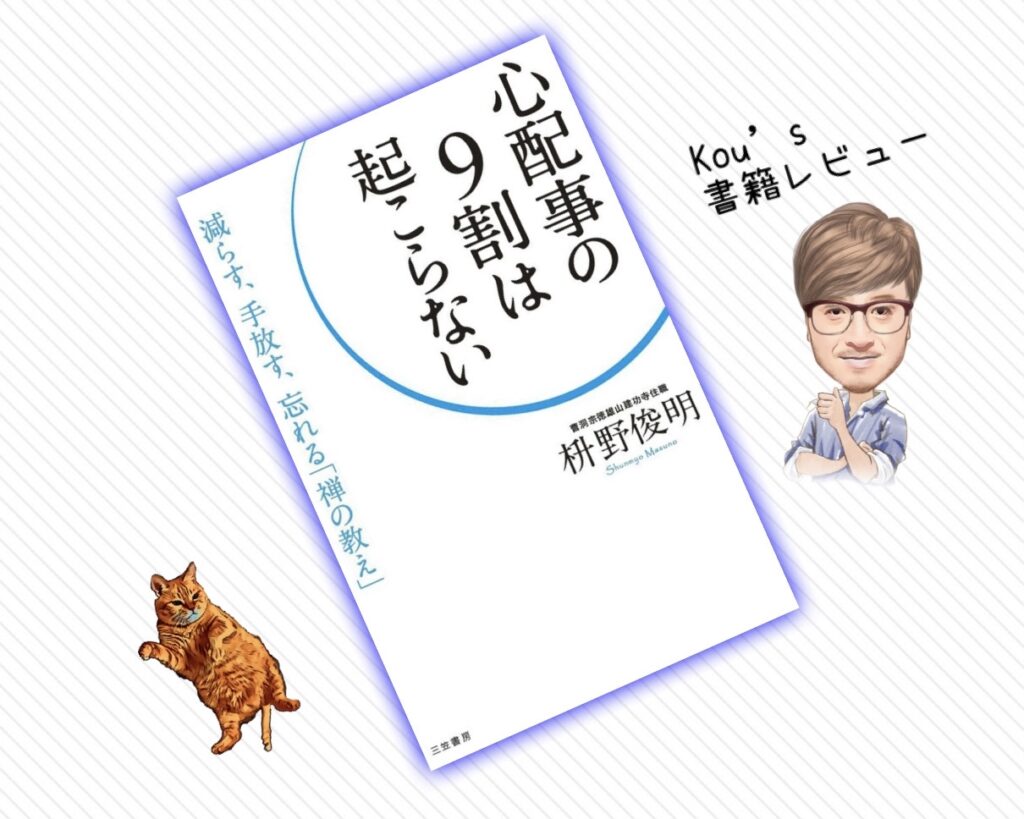

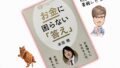
コメント