雨が降れば傘をさす
雨が降れば 人はなにげなく 傘をひらく
この 自然な心の働きに その素直さに
私たちは日ごろ あまり気づいてはいない
だが この素直な心 自然な心のなかにこそ
物事のありのままの姿 真実をつかむ
偉大な力があることを 学びたい
何ものにもとらわれない 伸びやかな心で
この世の姿と 自分の仕事をかえりみるとき
人間としてなすべきこと 国としてとるべき道が
そこに おのずから明らかになるであろう。
(PHP文庫「道をひらく」より)
「雨が降れば傘をさす」は、PHP研究所より刊行された、松下幸之助のエッセイ集「道をひらく」の冒頭を飾る、松下幸之助の考え方そのものともいえる代表的な一節ともいえます。
雨が降ってきて、そのままでいれば濡れてしまうが、傘をさすことによって濡れることを避けることができるように、そういった至極あたりまえの考え方や行動こそが人生の歩みのあるべき真理であり、そのように生きるには、なにものにもとらわれない「素直」な心であることの大切さも説いています。
わずか3人で細々と始めた事業から、一代で世界的な企業へと成長を成すことができたその大切な要因として、松下幸之助が事業体験を通じて培った、経営理念や経営哲学ともいうべきものの考え方の一遍一遍を、やさしく時に厳しく、現代を生きる私たちに新たな気づきを与えようと語りかけます。

松下幸之助(まつしたこうのすけ)
グレゴリオ歴1894年〈明治27年〉11月27日、ユリウス歴1894年11月15日 – 1989年〈平成元年〉4月27日)は、日本の実業家、発明家、著述家。 パナソニック(旧社名:松下電気器具製作所、松下電器製作所、松下電器産業)を一代で築き上げた経営者である。異名は「経営の神様」。 その他、PHP研究所を設立して倫理教育や出版活動に乗り出した。さらに晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだ。(Wikipediaより引用)
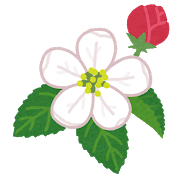
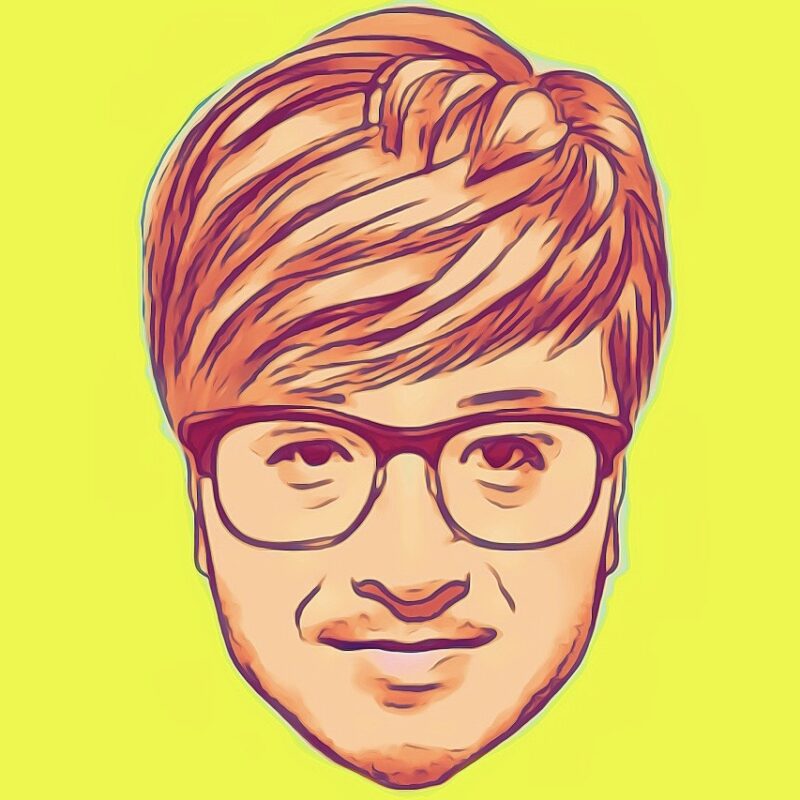
ここからは、本書を読んで、特に印象に残った3編を自己コメントとともに、抜粋して紹介していきます。
経営のコツここなりと気づいた価値は百万両 抜粋&レビュー
率先垂範が部下を動かす
主人公の率先垂範が第一ということは、まったく企業の大小を問わず、共通にいえることだと思います。
その表現の仕方は、それぞれの企業に応じておのずと違いはあっても、経営者は自分の責任を厳しく自覚し、一心不乱に仕事をしなければならない。
なにも意をたくましくする必要はない。
真実をさらけ出すことでいい。人はその姿を見て反応するのだ。
そう私は思います。
(本文中より)
「やってみせて、言って聞かせて、やらせてみて、 ほめてやらねば人は動かじ」
太平洋戦争下において第26、27代連合艦隊司令長官を務めた「山本五十六」の名言として現在においても人材育成の要としてよく知られています。
労働者側の視点で考えますと、その職場なり環境で前向きに働けるのは職場の理念なり労働環境にある程度の納得感を得ているからです。
なおかつ経営者の理念や事業へ向かう姿勢に共感できれば、この職場と経営者を信頼しようと本気で考えることもできるといえます。
先の、山本五十六の「やってみせて・・・」の言葉には続きがあります。
「話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。」と、締めくくられます。
信頼して任せるというのは、人を見極める眼力のようなものが必要ですし、権限などを移譲するにあたっては勇気もいります。
松下幸之助の言葉に、「人は信頼に値する」という言葉もあります。
そして、「人を信頼し任せて、万が一裏切られたとしてもそれもまた本望である」との言葉も残されています。
すべては人が創造し、受け継いでいくのも人であるという前提に立った、人を生かす経営に尽力した松下幸之助の考え方の真骨頂ではないかとも思える言葉です。
人の価値観が多様化する昨今においては、理屈をいくつ並べたてたところで反発をまねく場合がほとんどでしょう。
上に立つ者ほど飾ることなく、一心不乱に仕事をしつつ、周囲の人への感謝を忘れず、自らの理念やビジョンを共有することを地道に続けていくことです。
その謙虚かつ、本気の姿勢に感化され共感する人は必ず現れるものです。

好況よし 不況さらによし
好況のときはお客がどんどん買ってくれて品物が足りないくらいですから、問題はあまり出てきません。
しかし不況になれば、今度は買う人が、どこの店のどういうものがいいかということを吟味するようになります。
そうすると、それまで勉強していた店ほどよく売れるということになります。
店員の応対のよさとか、商品のよさが改めて目立ってきて、お客の方から買いに来てくれるということにもなります。
したがって、むしろ不況のほうがかえって忙しいということにもなるわけです。
(本文中より)
景気の良い時は、こちらから積極的にアピールしなくてもお客さんは来てくれますし、商品も飛ぶように売れていきます。
しかし一転、景気が悪くなれば客足は遠のき、商品も思うように売れなくなる傾向があります。
しかし、これはすべて景気のせいなのでしょうか。
世の中には、不況下においても業績を伸ばしている業界や、単独で繁盛しているお店などもあるのではないでしょうか。
不況となり、繁盛する店、撤退を余儀なくされる店の違いはどこにあるのでしょうか。
客足の絶えない店は、景気の良い時でも決してあぐらをかくことなく、しっかりと商品やサービスを良くするための創意工夫にあたったり、お客さんのフォローをしっかりとされていたのだと考えます。
反面、景気の良さにあぐらをかき、商品やサービスの工夫を怠たったり、あげくは、業績が良いのは自分の力だなどと、おごり高ぶり、お客さんを大切にしてこなかった店の結末は明白でしょう。
好況・不況は、波を打つように周期的にやってきます。
不景気の時よりも、景気の良い時の考え方や行動が要となるのではないでしょうか。
常に、謙虚に素直な心で事にあたるという心構えをもって行動できる人や店は、必然的に周囲の支持を集めることになり、「好況よし、不況さらによし」と力強く前に進めるのだと考えます。
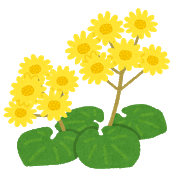
時代をつくっていく経営をしたい
その刻々に変わっていく時代についていくというのが、今日における一つの経営法だと思います。
また、そこからさらに一歩進んで企業が時代に先がけて、新しい時代をつくっていくという経営法もあると思います。
そのどちらかをやらなければなりません。
そうでないと、たとえ生き残ることはできても、発展は望めないのではないでしょうか。
(本文中より)
記憶に新しいコロナウィルスのパンデミックによって私たちの生活は激変しました。
それにともない、個人の価値観そのものも激変しているといっても過言ではありません。
経営者ともなれば、これからの世の中はこうなっていくだろうなどと、先見の目を養うことは必要です。
しかし、経営者も人間であるゆえに、「こうしたい」だとか「こうるはずだ」などと、感情が先行して事にあたるというのは、やもすると失敗の原因ともなりえます。
変化の激しい時代であるからこそ、現在の考え方は来年には通用しないと考えて、未来を想定し備えるといった思考が大切で、過去の成功体験にこだわるなどというのは一番のリスクとなります。
事を始めるにあたっては、熱意ありきで良くても、継続するにはその時代の傾向を分析しながら戦略をもって行動するという過程が必須といえます。
時代をつくっていくということは、常に謙虚に前向きに物事にあたるというところにあるのではないでしょうか。
事業を行うにあたるうえで、謙虚であるということは、時代をとりまく事象のひとつひとつを我がこととしてどう対処するかをしっかりと分析して、良い形で取り入れていくということだともいえます。
そのように時代の流れに対して謙虚であるためには、松下幸之助の言う、素直な心を持ち続けるということが最も大切なことなのだと考えます。
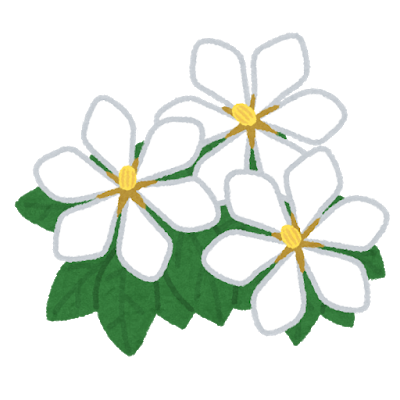
本書を読み終えて kou’s書籍レビュー
人は一人では生きられるはずもなく、何事も周囲の協力が得られてこそ、より大きなものにしていくことができますし、成功の確率もグンと上がります。
事業を始めるにあたって当初は孤独でも、規模が拡大するとともに志を共にする者の協力が必要となるでしょう。
そうした周囲の協力を得るには、まず自らの熱意と行動が先になくてはならず、将来のビジョンを明確に描き、具現化に向けて動き続けることです。
経営や商売のみならず、夢や、将来のビジョンなどの自己実現は、周囲の人の力添えがあってこその成果だと考え行動することが”コツ„だといえます。
本書での、”経営のコツ„ ”商売のコツ„とは、いわば”人生を豊かに生きるためのコツ„といってもよいのかもしれません。
そして「雨が降れば傘をさす」の言葉のとおり、あたりまえに起きることをあたりまえのこととして、謙虚に素直に対処していくという考え方も大切なのだと考えます。
それらの”コツ„に気づいたならば、その価値は”百万両以上„でしょう。
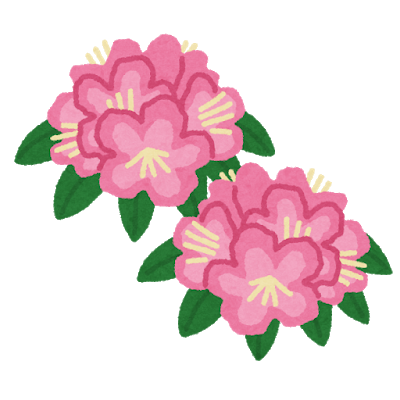
★この記事を書いた人★
 kou&バニ
kou&バニ
「本」こそが人生の師「KOU」と「バニ」です!
本を読み、先人の知恵や思考・生き方に触れることは、現代人にとっても良き人生をつむぐためのエッセンスとなりえます。
これまでも読書をするなかでは、多くの気づきと勇気を授かりました。
その数多くの「気づき」のひとつひとつは、血となり肉となり生き方を変えます。
書籍をもとに、人生をより良く変える思考を読み解きます。
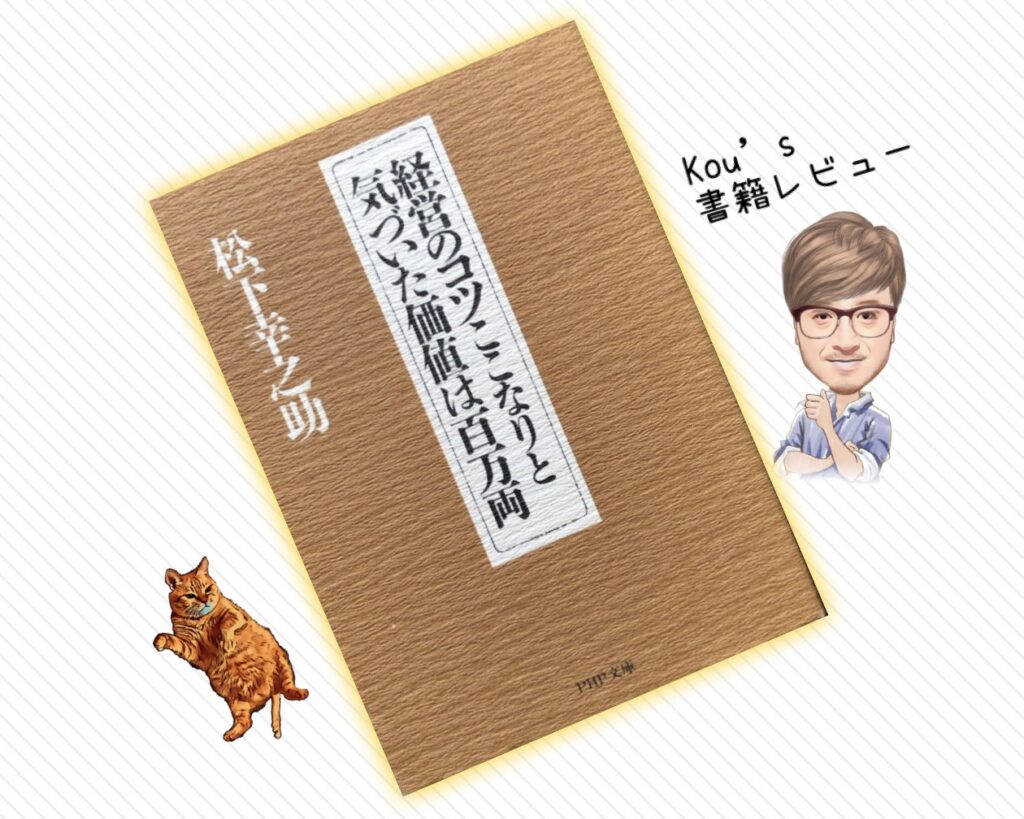


コメント