「1%の努力」と聞くと思い出すのが、トーマス・エジソンによる「天才とは、99%の努力と、1%のひらめきだ」の言葉を思い出します。
これにあえて反するような「1%の努力」とはどういうことでしょうか?
わたしたちが生きる社会は、すでに存在する価値観や常識によって形づくられています。
しかしそんな多くの価値観や常識は、今の時代に適応したものであるのでしょうか?
私たちを幸せにできるものなのでしょうか?
「努力」は必要だとしても、「努力」することを過度に美化されてはいないでしょうか?
それは、先人達が経験則にもとづき伝えてきた大切な考え方であることは間違いありません。
しかしそこに違和感を覚えるのであれば、古くなった常識のアップデートが必要なタイミングがやってきているということです。

価値観や常識は人それぞれですが、誰にとっても幸福に生きられるものであるべきです。
現状、何らかの息苦しさを感じるのなら、自らの考え方が時流に合っていないのだと理解しよう。
身のまわりにある価値観や常識を疑ってみよう。
本書で総じて語られるのは、常識を取り払ってものごとの本質をつかみ、効率よく最大の効果を求めようとする考え方です。
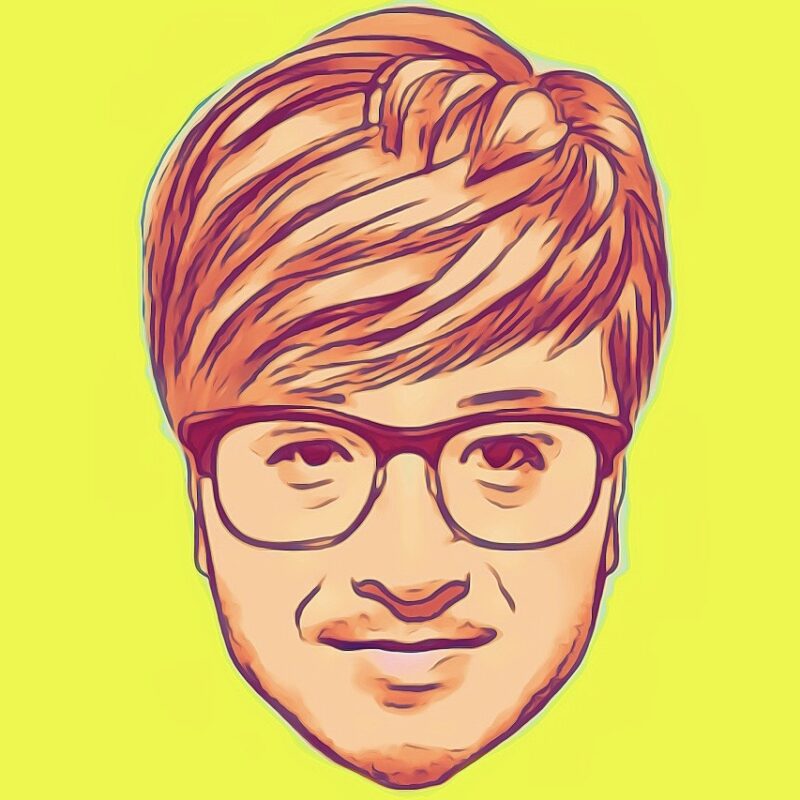
以下からは、各章ごとに「1%の努力」とは何なのかをより深く読み解いていきます!

著/ひろゆき(本名/西村博之)1976年、神奈川県生まれ。
1999年インターネット匿名掲示板「2ちゃんねる」の解説、管理人を経て、現在様々なメディアで活躍中。
「無敵の思考」「働き方完全無双」「論破力」など著書多数。
『1%の努力』書籍レビュー
レビュー① 団地の働かない大人たち 前提条件の話
「片手はつねに空けておけ」
少なくとも片手は空けておかないと、チャンスを掴むことはできない。
「努力で解決しよう」「頑張ればなんとかなるかも」と考えている人は、うねに両手が塞がっていてチャンスをとり逃す。
チャンスの神様には前髪しか無いといわれます。
まさに待ちかまえていなとチャンスの神様の前髪をつかむことはできません。
待ちかまえるには心に余裕がないとできません。
やるべきことを抱えこんではいけません。
スケジュールを埋めることよりも、スケジュールをあえて空けることを意識しよう。
日本人は勤勉だから、ヒマだと罪悪感を抱きます。
それこそが旧来の常識や価値観に毒されていると考えよう。
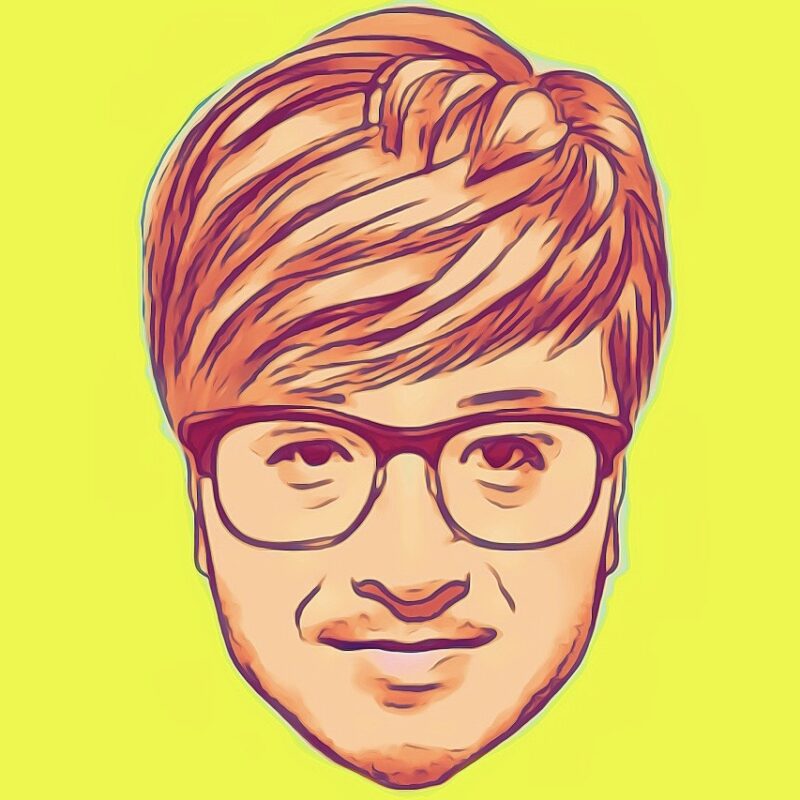
意図的につくる「ヒマ」は心の余裕で、人にやさしくなれます。
人にやさしくできる人には、より多くの人が集まります。
そんな人には、チャンスの女神のほうから寄ってくる!

レビュー② 壺に何を入れるか 優先順位の話
ユーチューバーが新発売のものをいち早く買ってきて箱を開く動画をあげたり、SNSで発信するようなことだ。
そうやって消費を体験へとつなげよう。
優先順位を決めるための思考法を持っておくと人生に有利だ。
人生を謳歌できているだろうか。
自分にとって大切なもの、絶対にゆずれないことはなんだろう。
自分の人生にとっての優先順位を誤ると、必要のないものが平然と入り込んできます。
「人に嫌われたくない。」
誰の心にもある感情です。
親、兄弟、伴侶、友人、先生、先輩、上司、部下・・・
それぞれがそれぞれの価値観にもとづいて、人生に入り込んできます。
自分は自分。他人は他人。
絶対に他人の価値観を受け入れてはいけません。
自分の人生を生きるには、受け入れていいのは自分だけ。
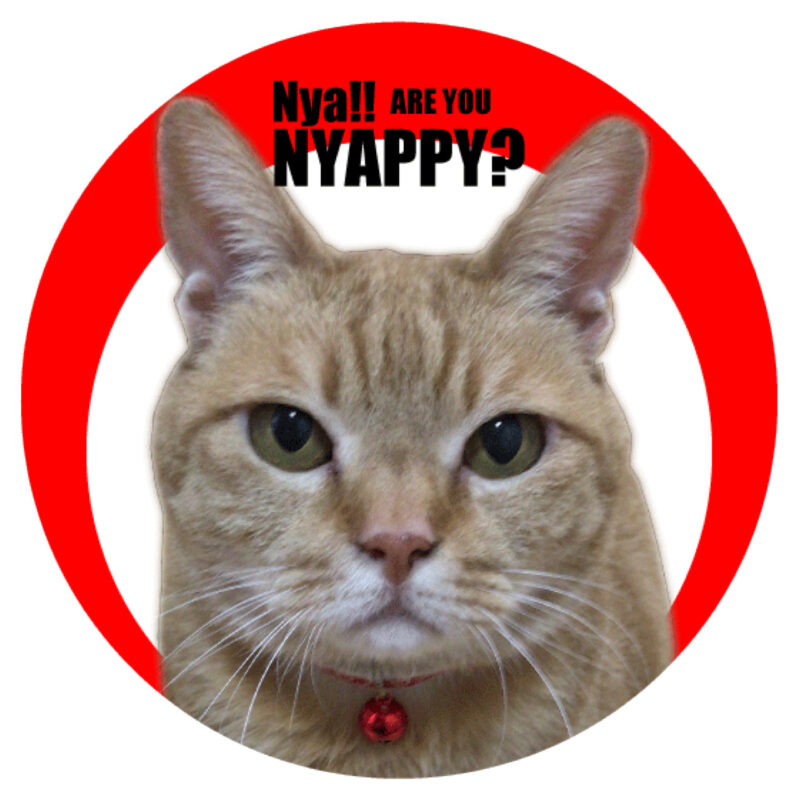
他人の人生を生きてはいけない!
自分の人生を生き、謳歌するのだ!

レビュー③ なくなったら困るもの ニーズと価値の話
「この体験が、なくなったら困るな」と、あなたがそう強く感じられるものを安定収入にするのがいい。あるいは人生を捧げてもいいかもしれない。
そこには第三者の意見が入る余地はない。
誰がどう思っているかは、どうでもいい。
ハマっているものがありますか。
熱中し、没頭できるものがありますか。
それは、この世からなくなったら困りますよね、
それは、生きるうえで何にも代えがたいものです。
昨今は、今後の人生を考える機会は多いでしょう。
しかし、老後やお金など、よぎるのは不安でしょう。
未来は分からないから、人間は未知なものには不安や恐怖を感じます。
不安を遠ざけるには、自分の大好きなものにハマること。
没頭し、ハマることで、その分野のマニアや専門家となれます。
世にニーズが生まれれば、ビジネスとなります。
お金が頂けることになるかもしれません。
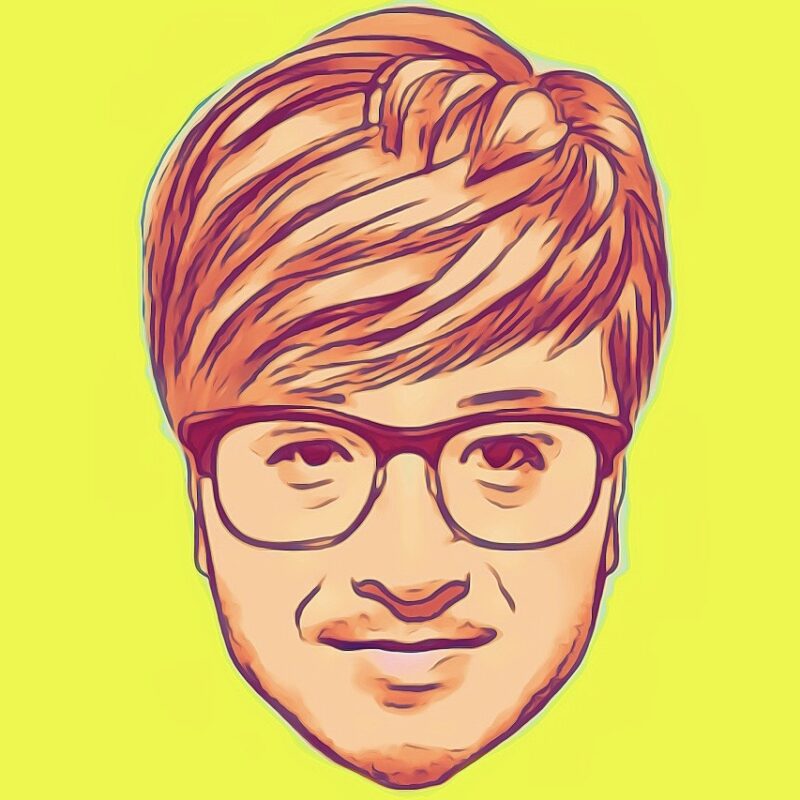
「大好き」の気持ちは不安を遠ざけ、ワクワクで満たされる!

レビュー④ どこにいるかが重要 ポジションの話
下っ端仕事でグチばかり言っているとしたら、一度、経営者側として自分だったらどうするかを考える。
あるいは店長のような立場だったら、現場の仕事で知らない部分がないかを考えてみる。
それだけであなたは頭一つ飛び抜けることができるだろう。
仕事は楽しいですか?
仕事は一生懸命するもので厳しいものだという人もいます。
もちろん仕事にはそういった側面もあるでしょう。
仕事には人生の半分以上の時間を捧げます。
それだけ多くの時間を捧げるものであるからこそ、楽しいものでありたい。
光と影、どこに注目するか。
いま仕事が楽しくないなら、ささいなことから始めてみよう。
「出社したら誰よりも大きな声で「おはようございます!」と言おう。」
「誰よりも早く電話をとってみよう。」
「報連相(報告・連絡・相談)を徹底してみよう。」
「仕事があることに感謝してみよう。」
簡単なことのようですが、できている人は少ないです。
これだけでも徹底できれば、人より抜きん出ることができます。
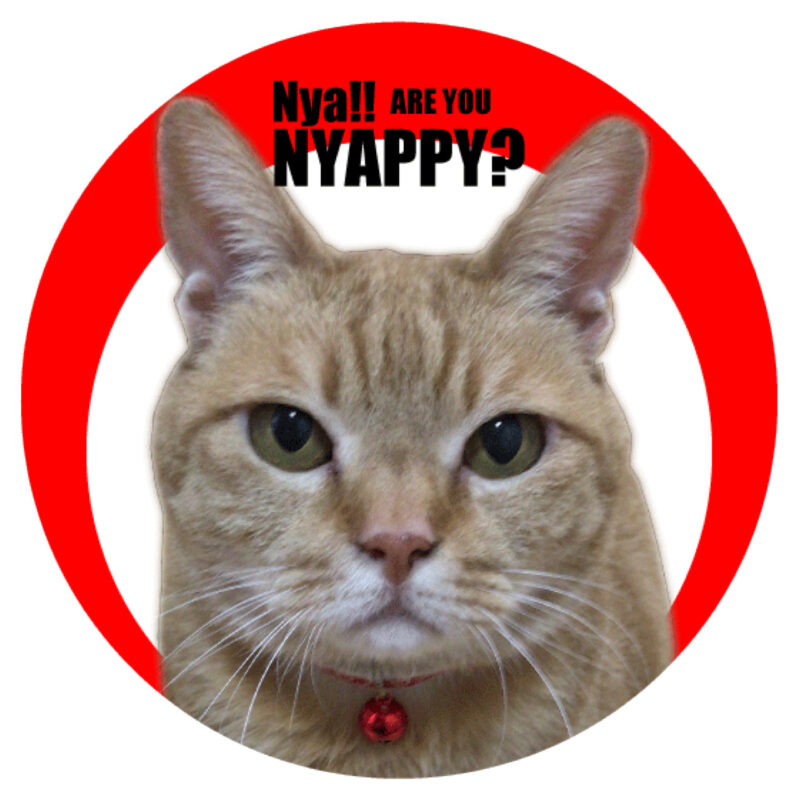
人よりも抜きん出てくると、周りが放っておかない。
結果、人生が変わっていくぞ!

レビュー⑤ 最後にトクをする人 努力の話
中学生・高校生男子に人気のスポーツは野球とサッカーとバスケだが、日本人ではバスケだけで食える人は極端に少ない。
そういう意味では、同じ身体能力を発揮できるなら、野球やサッカーに早めに移ったほうが食っていける可能性は高い。
そうやって、自分の能力を睨みながら社会のニーズに合わせられる人のほうが、世の中では成功しやすい。優秀な会社員としても向いている。
何年も何十年も大好きな一つのことに取り組んできた。
やがて、これで飯を食っていきたいと考えます。
しかし、世の中にそれを「お金を出してでも欲しい」という人がいなければ、飯は食えません。
「需要と供給」
求める需要側と与える供給側があって、経済がまわります。
これはいつの世であっても、変わらない原理原則。
それを認めず、自らの思いに固執する人もいます。
「執着」
これはやっかいもので、一度持つとなかなか手放せません。
プライド?世間体?
変わり身を阻害するものは多々あります。
食べていけなければ生きていけず、やりたいことすらできません。
まずは食べていける状態をつくりましょう。
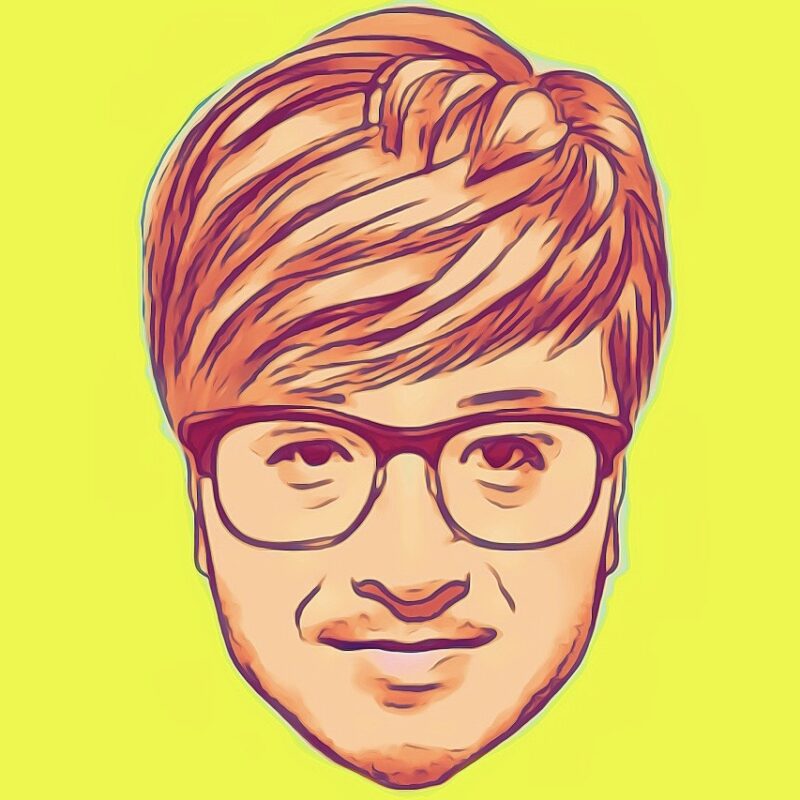
まずは、生活の基盤をつくること!
やりたいことなら、そのあとで思いっきりできますよ。

レビュー⑥ 明日やれることは、今日やるな パターン化の話
コードを書いているときに不思議なことが起きる。
うまくいくときはどんどん書けるし、うまくいかないときは全然書けない。
早めに諦めて寝て、次の日になると、あっけなく解決してしまうこともある。
ダメなときに、素早く諦めることも、「1%の努力」には必要な要素である。
徹夜して体を壊したら、元も子もない。
一般的に学校や職場では、こんな教育をされます。
「今日やれることは今日中に」
「明日は明日やるべきことがある」
このような考えに固執していると、生産性の低下をまねくケースもあります。
たとえば、試験。
難しい問題につかまっていては、時間切れとなってしまいます。
そういうときは、解ける問題から解いていく。
試験攻略には必須のテクニックであることはいうまでもありません。
対峙する問題に真っ向勝負してはよくない場合もある。
状況により、いさぎよく諦めて、いったん退き冷静になってみよう。
インターバル時間を経ることで、以外にあっさりとその問題が片づいたりすることもある。
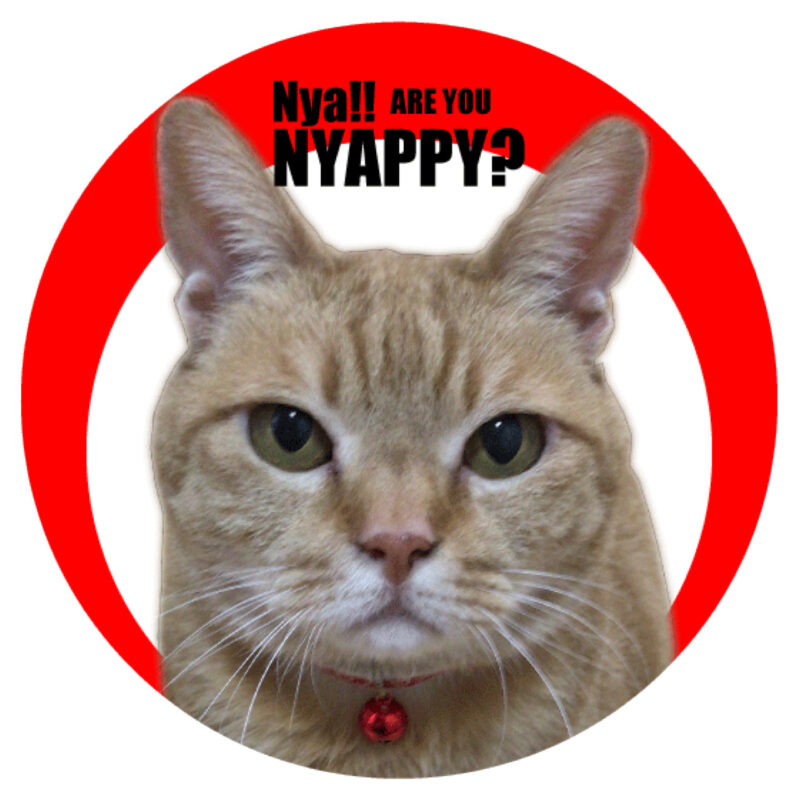
ここでの「1%の努力」とは、戦略を持つこと!
”要領の良さ”といってもいいかもしれないね。

レビュー⑦ 働かないアリであれ 余生の話
「働かないアリ」は、ぶらぶら歩いていると、思いもよらなかったデカいエサに出くわす。
巣に戻り、エサがあったことを知らせると、働きアリが運んできてくれる。
さあ、あなたはどちらのアリになりたいだろうか。
サボる才能はあるだろうか。
「サボる」という言葉にどのようなイメージがありますか?
「サボる」という言葉や行為に、「良くないことだ」というイメージがありませんか?
アリの世界には、それぞれに生まれもった使命、役割があります。
働きアリはエサを運んだり、巣のメンテをしたりして働きます。
働かないアリは外に出てエサをみつけて報告し食糧を確保することを生業とします。
それぞれに本能的に持った特徴をそれぞれに活かし、ささえながら生きています。
そこには良いも悪いもありませんし、働きアリがグチを漏らすなんていうことも無いでしょう。
何をするにせよ、煮詰まったときにはいさぎよく「サボる」ことをしてみよう。
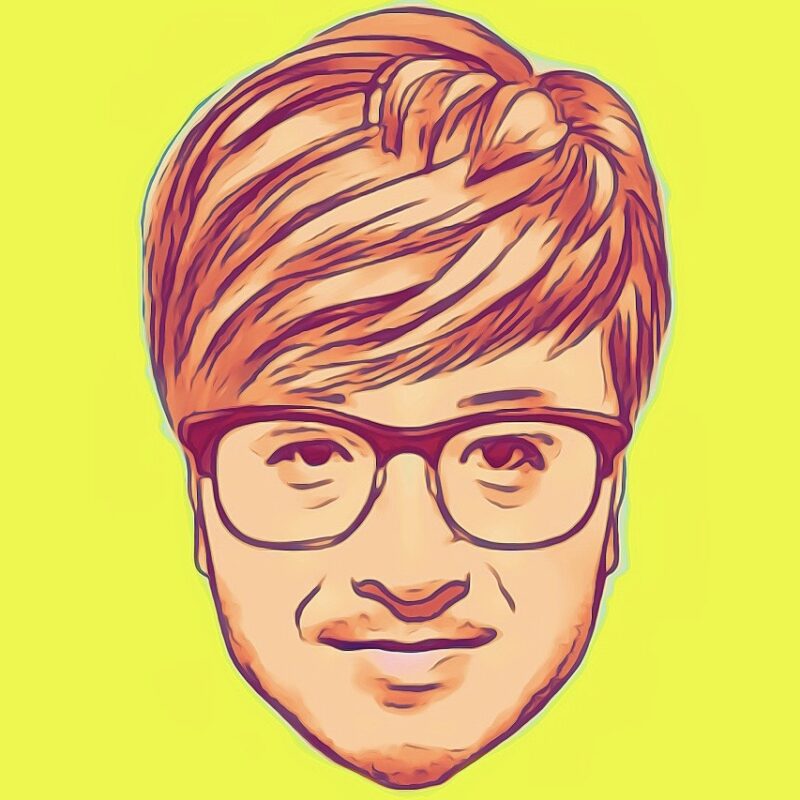
「時間をおく」「気分転換をする」「ぐっすり寝る」
戦略をもって「サボる」ということは、むしろ生産性を改善することともなる!

まとめ 本書を読み終えて
「新型コロナウィルス」のパンデミックによって、多くの人がこれまでの生き方を見つめなおす必要に迫られました
これまであたりまえとされてきた、常識や価値感はガラリと変化しました。
「仕事優先、長時間労働、上下関係遵守、終身雇用、貯金・現金主義・・・」
しかし、まだ以前の古い常識や価値観にしがみついて生きている人も少なくありません。
住みなれた土地や家が居心地がいいのと同じで、変化を恐れています。
そういった生き方を否定はしませんが、今後はとても生きづらくなります。
夏休みの宿題を8月の終盤になってあわてて取り組んだ経験は、心あたりがある人も多いでしょう。
そして、せっぱつまり、提出日に間に合うわせるために、頭をフル回転させたのではないでしょうか。
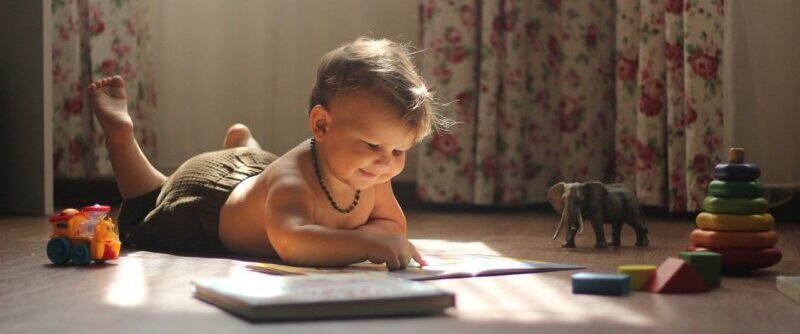
一般的に、ものごとを先延ばしにする人は否定され、計画的にすすめられる人は肯定されます。
しかし、両者とも長所と短所があるともいえます。
前者は、遊びの時間を優先したツケとして、作業の時間はかぎられますが、「火事場のバカ力」とでもいうべき、突破力という才能を発揮しています。
後者は、余裕のある心穏やかな時間を得ることができますが、自然や遊びの中での学びを深く追求できていたでしょうか。
これまでの常識を疑って、別の角度から考えてみる。
こんな考え方のなかに「1%の努力」があります。
「1%の努力」を自らに取り入れていくことで、生き方が断然「ラク」になるでしょう。
「ラク」をすることの前提に思考があれば、「ラク」はけっして怠惰なことではありません。
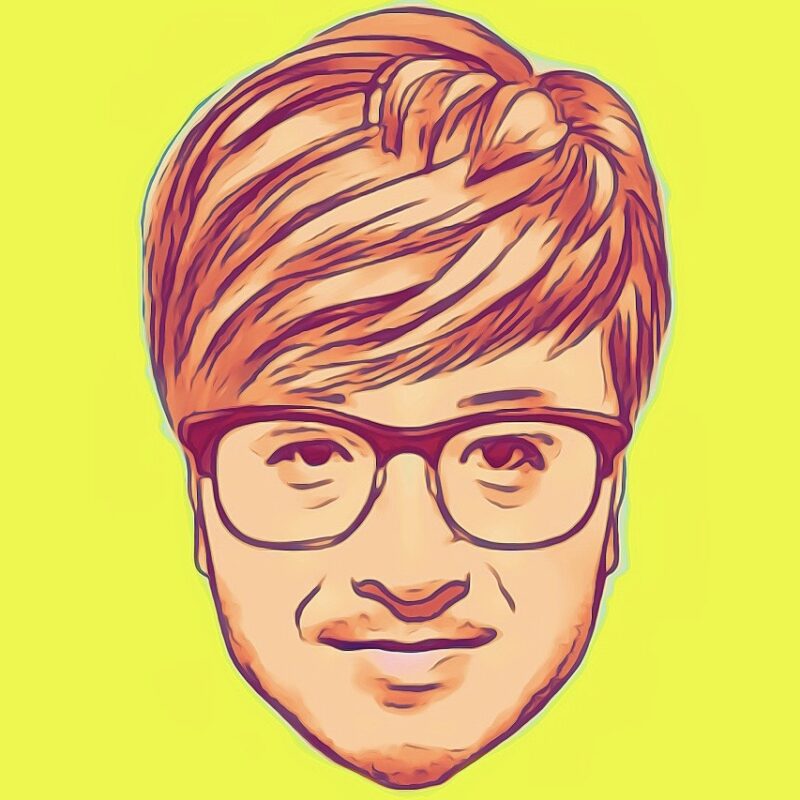
新型コロナウィルスのパンデミックによって、人の価値観が変化しています。
働き方や生き方にも多様化が進んでいるといってもいいね。
努力、忍耐など、これまで美徳とされてきた一般通念にも疑問を感じます。
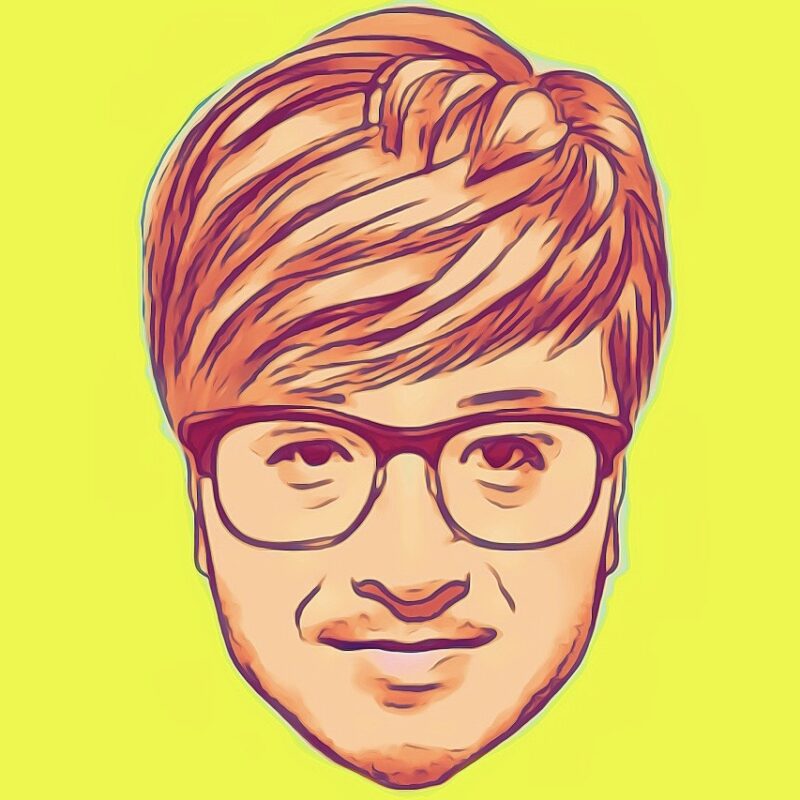
努力することは理想を手にするためにも必要なことでもあるし、忍耐することも好機のタイミングをつかむためにも必要な学びの時間なのだろう。
しかし、このようなある種の固定観念に固執して、視野が狭くなってしまい、自らを苦しませてしまっては元も子もないと思う。
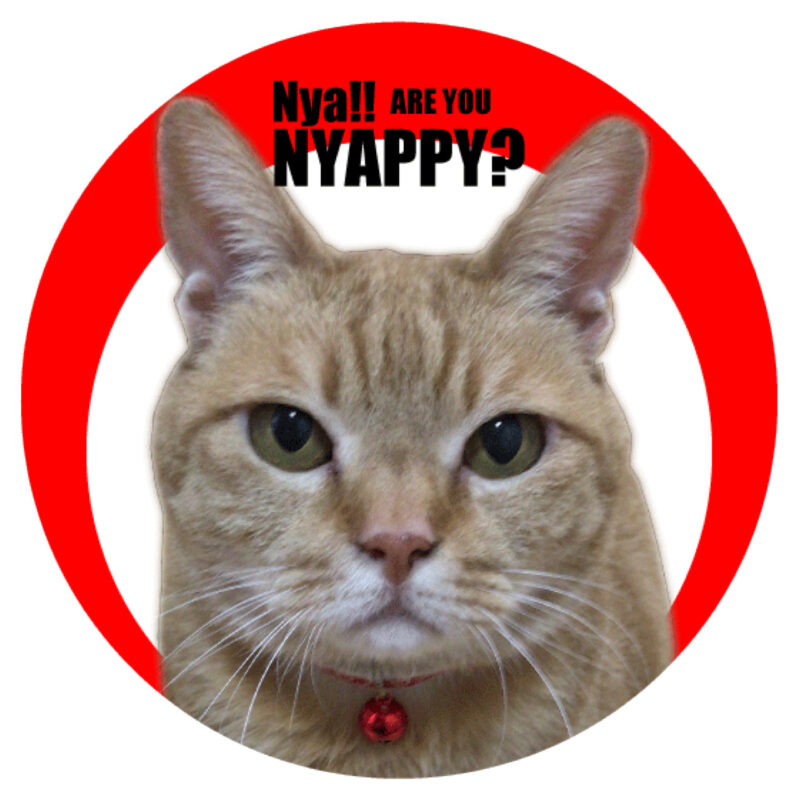
ここでいう「1%の努力」とは、時流にあわせて自らを変化させていくといってもいいね。
『最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き残るのでもない。唯一生き残ることができるのは、変化できる者である。』は、ダーウィンの言葉としても有名だね。
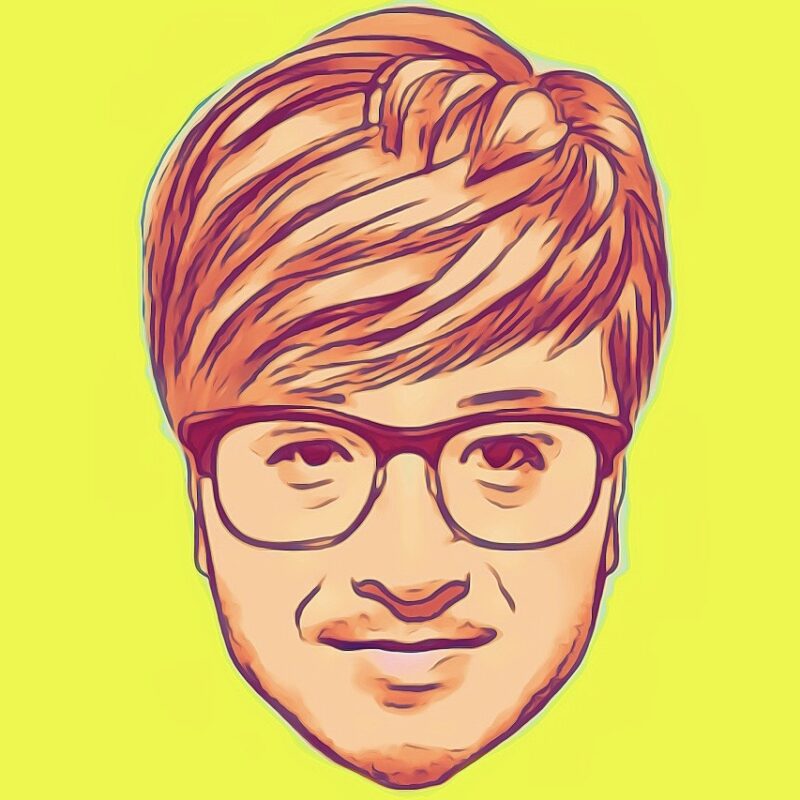
とにかく、現状、何らかの息苦しさを感じているなら、あたりまえにある常識を疑ってみることから始めてみるといいと思う。
そこで新たな考え方に気づき、受け入れられたときが変化のときで、新たな人生のスタートとなります。
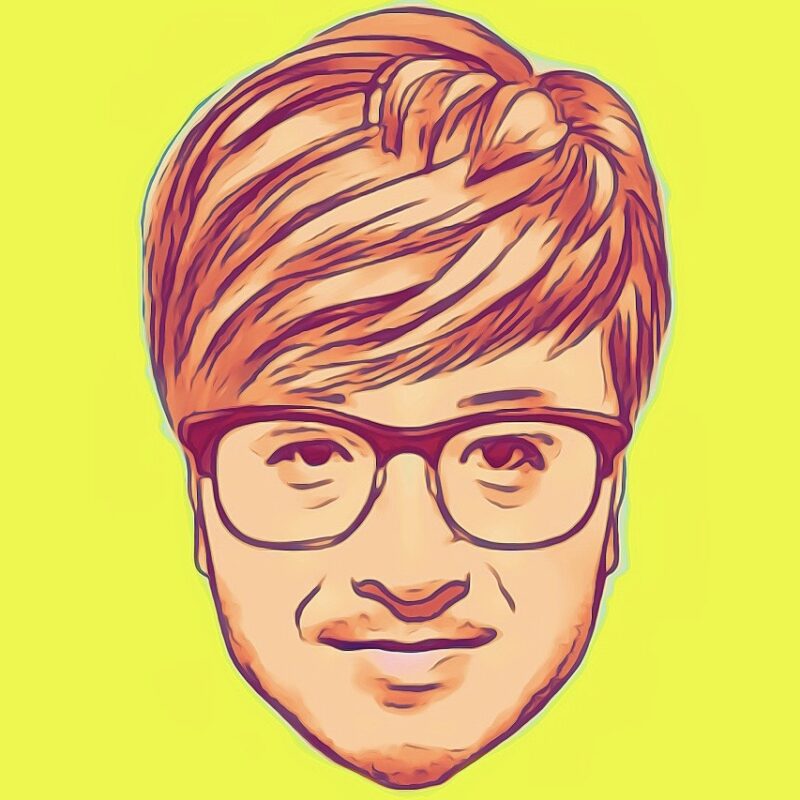
時流とともに変化できる柔軟な心こそが、「1%の努力」といえる。
ぜひ、ご自身なりの「1%の努力」の手段をみつけてみてほしい。
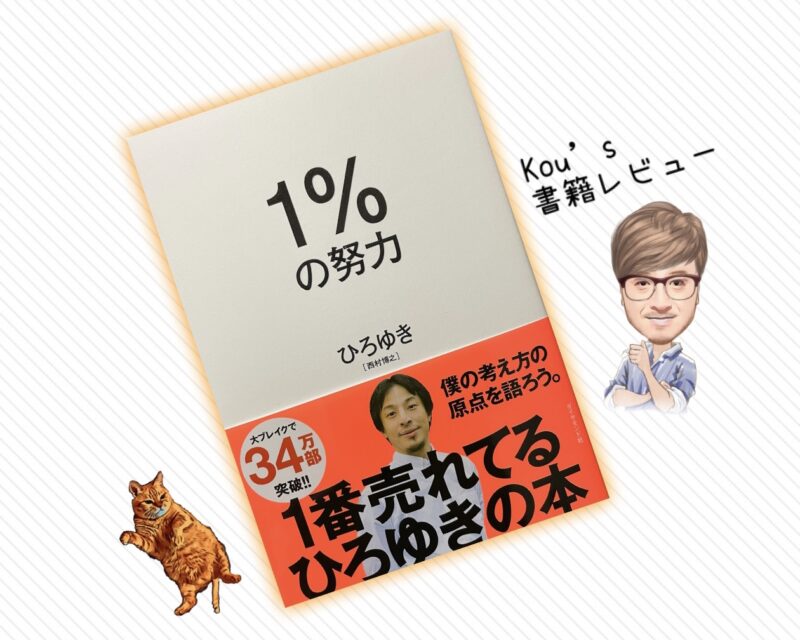


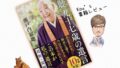
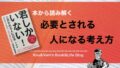
コメント