質問です。
あなたの生きがいとは何ですか?
そして、あなたは歯車ですか?
社会?
会社?
家庭?
歯車という言葉に対してどのようなイメージをもっていますか?
なんとなくネガティブな印象を持っているのではないでしょうか?
なぜ、ネガティブなのか?
お金のため?
家族のため?
会社のため?
世間体を気にするから?
とにかく、生きていくため?
こんな疑問を改めて投げかけられた一冊に出会いました。
「コンビニ人間」 村田紗耶香/著
村田 沙耶香(むらた さやか/1979年8月14日~)は、日本の小説家、エッセイスト。

本書「コンビニ人間」との出会い
偶然ある小冊子で、村田紗耶香さんのコラムを目にし、おしげなく性根をまき散らすような文章に圧倒的迫力を感じました。
第一印象で、「やばいなこの文章は(汗)」
と、衝撃とともに魅了されてしまったというのが始まりでした。

後日、偶然、本書「コンビニ人間」を手に取り、著者が村田紗耶香さんとのことで迷わず購入。
芥川賞を受賞した作品といううことは知る範囲でしたが、そのコラムを目にするまではは特に興味を抱くことはありませんでした。
あの、迫力の文章をもう一度味わいたい!との思いで、一気に読みすすめます。
辛辣な文章と尖った言いまわし、ど!ストレートな表現に理屈なく引き込まれます。
コンビニの空気感、従業員の人間性や体温まで伝わってきそうな表現は圧倒的にリアルです。
自分もコンビニ勤務の経験があるということもあるかもしれません。
難解な言葉や表現などもおさえられていて、ストーリーのテンポも軽やか、長すぎず短すぎずで読みやすい作品でした。

コンビニ人間の物語
現在では日本のコンビニは5万店舗を越え、誰にとっても身近で生活に欠かせないインフラとなっているコンビニが本書の舞台です。
主人公の古倉恵子はアルバイト歴18年の彼氏なしの36歳。
彼女はコンビニで働くことが、唯一社会との接点として生きています。
彼女にとってコンビニという存在に従属し、その一部分、ある意味「歯車」になることが生きることの何かを実感する全てです。
それは、やりがいなどというものではなく、「存在意義を実感する場所」として存在します。
物語では店内の空間描写や、職場としてのコンビニが取り持つ様々な人間模様が淡々と描かれていきます。
多様な人格が交わることでコミュニティーを形成し、誰もが同じ目標のもと、働く喜びに共感していきます。
しかし、「昨日の友は今日の敵―――」
あるきっかけで、親しかった身近な人たちでさえ、人間の弱さ醜さや本音をあらわにしていきます。
やがてそれは一般社会の縮図となってゆっくりと増殖し、恵子の人生は、なかば強制的に転換期をむかえます。
葛藤のなか、恵子は人生を振り返り模索し続けるのですが。。。

世間の常識や先入観に対する葛藤
フリーターを経験したことのある方なら特に共感できるかもしれません。
アルバイト職種への偏見。
定職に就かないことへの世間からの風当たり。
人と異なることのメリットとリスク。
普通であることの価値とは?
そもそも人と異なることの基準はどこにあるのか?
人間関係と世間の目。
同調して生きていることとは?
現代社会のなかで、あたりまえとされる常識。
敷かれた人生のレールを歩むことの価値。
はたしてそこに自分は存在するのだろうか。
彼女はこのような疑問や問題に対峙し、もがきながら進むべき道を探し求めます。

本書を読み終えて kou’s書籍レビュー
本物語のラストでは、そよ風のような爽やかさを感じるとともに、彼女の今後の人生に一抹の不安を覚えてしまいました。
その不安の正体は何かと考えてみると、自分にも固定観念や先入観がしっかりと根付いていていることに気づかされます。
人生経験があればあるほど、この邪魔者を取り払うのは容易ではありません。
それでも今後の彼女の人生を応援していきたいとの願いは、誰しも思い抱くはずです。
彼女の選択が私たちの願望や生き方とも重なり、共感できるからです。
本書「コンビニ人間」には、私たちの人生の縮図と共通する世界観が息づいています。
例えるなら―――
「銀杏の実」のように、甘味のあとにじわりと苦みをともなう人生の味わいがあります。
物語のラストで恵子はどのような選択をし、どう生きようとするのか?
ぜひ、ご自身で確かめてみてはいかがでしょうか。。。
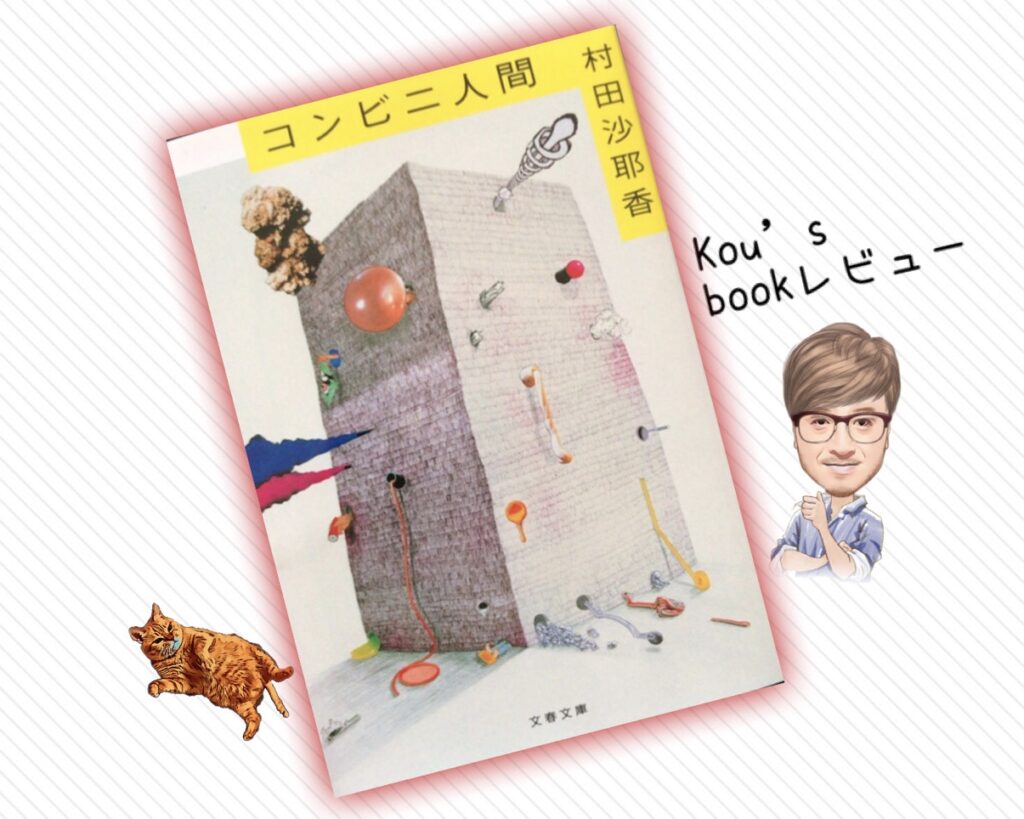


コメント