不安はありますか?
まったく不安などないという方は少ないでしょう。
不安を感じる割合が多くなると、人は様々な弊害をともなうこととなります。
不眠に悩んだり、悪くすれば健康に害をも及ぼしかねません。
仕事のパフォーマンスにも影響をあたえてしまいます。
喜怒哀楽という言葉があるように、人間生きていく上では切り離せない「不安」という感情は、あってあたりまえといってもいいものです。
しかし、できれば不安なく平穏に生きていきたいと願うのも人としてあたりまえの感情です。
不安とは、不確定の未来の要素から人が勝手につくりだしているもので、生きていくうえでの防衛反応といってもいいでしょう。
どのみち抱いてしまう感情ならば、上手に付き合っていったほうが得策なのではないでしょうか。
まずは、不安というものを理解していくところから始めてみましょう。
では、この「不安」とどのように対処し付き合っていけばいいのか?
不安をから目をそむけず、その不安はどのような原因から出てきたものなのか?
そのヒントとして、「不安を消すコツ」上西 聰/著 を紹介します。
植西 聰(うえにし あきら、1947年-)は、東京都出身の日本の著述家、産業カウンセラー、心理カウンセラー。(Wikipediaより)

「不安を消すコツ」抜粋&レビュー
人生は「なるようにしかならない」とひらきなおってみる
ここでは、「一寸先は闇」という格言になぞらえ、一寸(約3センチ)先の未来もわからない人生に悩み不安を抱くのは取り越し苦労であるとしています。
たしかに、未来のことがわかったり、準備できたりするのなら苦労はありません。
そもそも不安に思うことが事前にわかれば、不安にすらならないでしょう。
私たちは未来を良くしたいと思えばこそ「今」を懸命に生きています。
ならば、未来へとつながる「今」この「瞬間」こそを大切にして生きてみましょう。
「人事を尽して天命をまつ」という格言のとおり、懸命に今できることをやり、あとは「なるようにしかならない」とひらきなおってみることこそが不安を消していくコツといえます。

不安な気持ちになって来た時には、適度な運動をする
適度な運動や体を動かすことは心身の健康のみならず、精神面でもよい影響を与えます。
散歩やジョギングなど体を動かすことはもちろん、日光を浴びることで「セロトニン」という別名「幸せホルモン」「快楽物質」とよばれるホルモン物質が脳から分泌されます。
これにより、爽快さと同時に気持ちも前向きになるという恩恵にも与れます。
そして気持ちが前向きになり、知性が活性化することで自尊心も高まります。
自尊心が高まると、様々な問題に対しても「自分ならできる」「なんとかなる」と、ポジティブにとらえられるようにもなってきます。
立ち止まって考えていたところで何も解決することはありません。
悩んだり不安に思うことで頭がいっぱいになってきたら、思い切って身体を動かしてみましょう。
適度な運動を習慣化することで、ものごとのとらえ方に劇的な変化を実感できるはずです。

自宅での「やすらぎの時間」を大切にする
あなたは仕事のON、OFFのメリハリはつけていられてますか?
良い仕事をするためにも、プライベートな時間も大切にしましょう。
そのためにも自分自身が安らげる場を確保しましょう。
あなたは自宅で安らげていますか?
自宅こそは疲れを癒し、心の安定を取り戻す唯一の場所でありたいですね。
社会生活を営むうえでは、多くのストレスと向き合わなければならず、避けて通ることは困難です。
ならばそのストレスと上手に付き合っていければ、いわば無敵状態を目指せます。
ストレスに真っ向勝負を挑むのではなく、ストレスと上手に付き合っていきましょう。
発想を柔軟に変えていくことが重要です。
家族との団らんや、大好きな趣味に没頭したり、自分のやりたいことをする時間を大切にしましょう。
それを習慣化できれば、自宅こそが安らぎの場、回復の場となって次なる仕事や課題へも新鮮な気持ちで挑めるようになります。
そこには、不安などないはずです。

本書を読み終えて kou’s書籍レビュー
本書、「不安を消すコツ」から、印象に残った3編をもとに紹介してきました。
不安を消すには、日常の些細な習慣を見直すことにヒントがあります。
不安とは、感情を持つ人間ならごく自然にあることとして上手に付き合っていきましょう。
結局のところ、不安とは不確定な未来に対して人が勝手につくりだしたものです。
そこに根拠などなく、ほとんどの不安は実現されません。
自己肯定感が低いと、ものごとを悲観的に考えがちとなります。
今日から、自分から積極的に行動することを心がけましょう。
そう、自己肯定感を高める行動をとっていくのです。
自分の願望、本当はどう考えているのか?
本音は、何をしたいのか?
自分の思いを優先して行動する習慣をつくりましょう。
自分の気持ちに忠実になればなるほど自己肯定感が育まれ、不安を感じることも少なくなるでしょう。
本書には、ここでは語りきれない多くの不安との向き合い方のヒントが散りばめられています。
自分に合った方法やヒントが必ず見つかるはずです。
あなたが抱いている「不安」の正体をぜひご自身で確かめてみてはいかがでしょう。
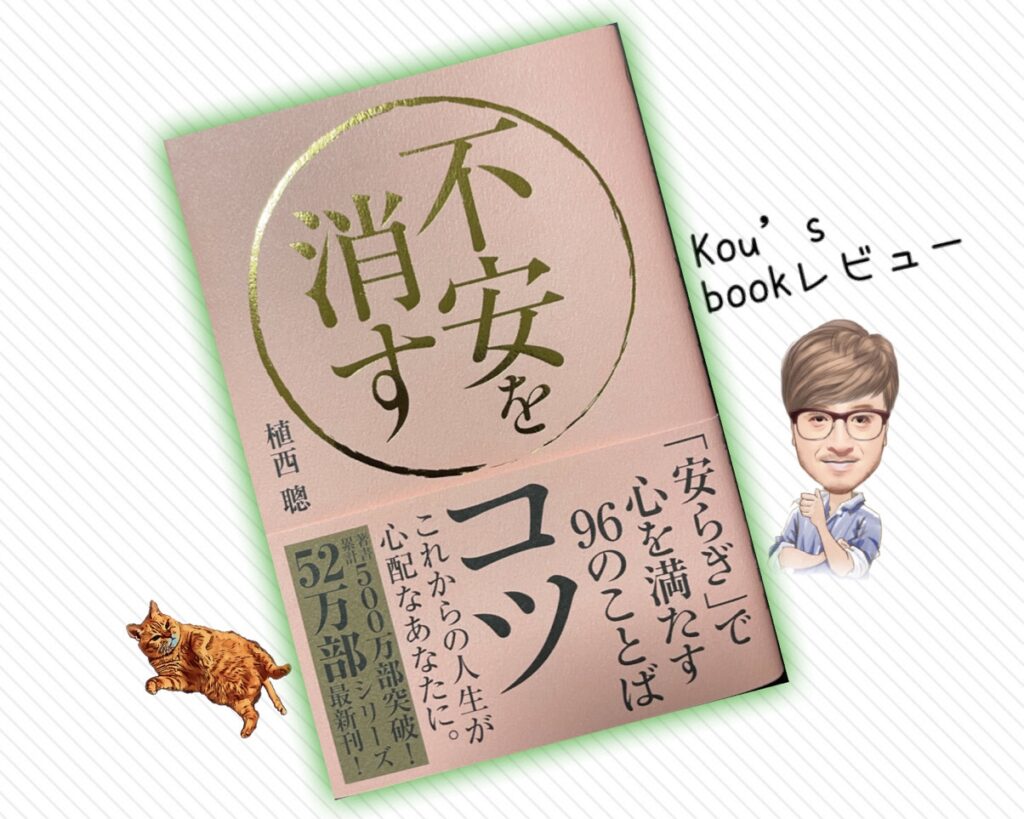
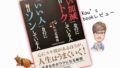

コメント