雨が降れば傘をさす
雨が降れば 人はなにげなく 傘をひらく
この 自然な心の働きに その素直さに
私たちは日ごろ あまり気づいてはいない
だが この素直な心 自然な心のなかにこそ
物事のありのままの姿 真実をつかむ
偉大な力があることを 学びたい
何ものにもとらわれない 伸びやかな心で
この世の姿と 自分の仕事をかえりみるとき
人間としてなすべきこと 国としてとるべき道が
そこに おのずから明らかになるであろう。
(PHP文庫「道をひらく」より)
「雨が降れば傘をさす」は、PHP研究所より刊行された、松下幸之助のエッセイ集「道をひらく」の冒頭を飾る、松下幸之助の考え方そのものともいえる代表的な一節ともいえます。
雨が降ってきて、そのままでいれば濡れてしまうが、傘をさすことによって濡れることを避けることができるように、そういった至極あたりまえの考え方や行動こそが人生の歩みのあるべき真理であり、そのように生きるには、なにものにもとらわれない「素直」な心であることの大切さも説いています。
わずか3人で細々と始めた事業から、一代で世界的な企業へと成長を成すことができたその大切な要因として、松下幸之助が事業体験を通じて培った、経営理念や経営哲学ともいうべきものの考え方の一遍一遍を、やさしく時に厳しく、現代を生きる私たちに新たな気づきを与えようと語りかけます。

松下幸之助(まつしたこうのすけ)
グレゴリオ歴1894年〈明治27年〉11月27日、ユリウス歴1894年11月15日 – 1989年〈平成元年〉4月27日)は、日本の実業家、発明家、著述家。 パナソニック(旧社名:松下電気器具製作所、松下電器製作所、松下電器産業)を一代で築き上げた経営者である。異名は「経営の神様」。 その他、PHP研究所を設立して倫理教育や出版活動に乗り出した。さらに晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだ。(Wikipediaより引用)

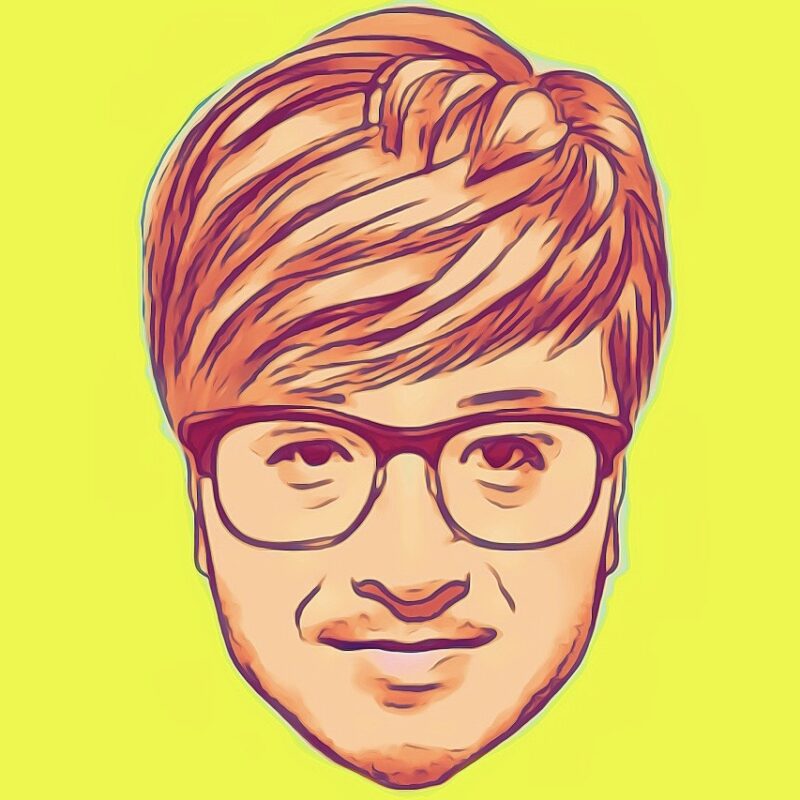
以下から、本書を読んで、特に印象に残った3編を抜粋して、自己コメントともに紹介します。
実践経営哲学 松下幸之助 書籍抜粋レビュー
人間観をもつこと
経営は人間が行うものである。
経営の衛にあたる経営者自身も人間であるし、従業員も人間、顧客やあらゆる関係先もすべて人間である。
つまり、経営というものは、人間が相寄って、人間の幸せのために行う活動だといえる。
したがって、その経営を適切に行っていくためには人間とはいかなるものか、どういう特質をもっているのかということを正しく把握しなくてはならない。
いいかえれば、人間観というものをもたなくてはならないということである。
(本文中より)
「企業は人なり」ということはいうまでもないことですが、経営者のみならず、経営に関わるすべての活動そのものが人がつくりだす創造活動だといえます。
人が労働に従事する動機や理由はさまざまですが、その職業や職場の選択の場面においては、仕事内容や労働環境、ひいてはその会社の経営理念に共感したもの同士が集まっているともいえます。
日々、生活の糧を得る仕事の中においても働く目的や、ささやかながら自己実現を夢見て日々努力されている人もいらっしゃいます。
こうした人間の心情を汲み経営を指揮するといったところ、さらに言うならば、個々の能力、個性を積極的に発揮できる環境づくりに徹するということこそが、人間観をもって経営にあたるということなのだと考えます。
人、物、資金などに対して、愛情と公正さと十分な配慮をもってあたっている職場や経営者にこそ人は信頼感を抱き、その対価として、個々の能力や時間を労働力として惜しみなく提供していけるのだと考えます。
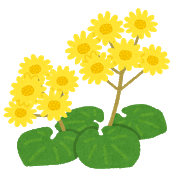
利益は報酬であること
企業は、どのような社会情勢の中にあっても、その本来の使命の遂行に誠実に努力していくと同時に、その活動の中から適正な利益をあげ、それを税金として国家、社会に還元していくことに努めなければならないのである。
それは企業にとっての大きな責務だといえよう。
(本文中より)
人がお金を支払い物を買うのは、その対価となる商品やサービスにそれ以上の価値があると判断できたときです。
企業が供給する商品やサービスの中に含まれる企業努力や社会奉仕の度合いが大きければ大きいほど、その商品やサービスの価値は大きくなり、需要も増します。
そのような価値ある商品やサービスを供給する企業は需要や社会貢献度も大きくなり、原則としてそれに見合った報酬としての利益を受け取ることになります。
ゆえに価値ある商品やサービスを提供できる企業は、報酬としての利益を受け取り、適正な税金を納め、株主への還元といった役目を果たすことでの社会貢献も可能となります。
しかし過剰な利益追求を至上の目的として、企業としての本来の役目・使命を忘れ、目的のために手段を選ばずことを運ぶという姿は決してあってはなりません。
利益とは、社会にとって価値ある商品やサービスを提供できた経営活動に対する社会からの感謝の気持ちが利益として報酬となっているということを決して忘れてはなりません。
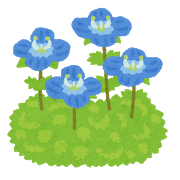
時代の変化に適応すること
経営理念を現実の経営の上にあらわすその時々の方針なり方策というものは、これは決して一定不変のものではない。
というよりも、その時代時代によって変わっていくのでなければならない。
いいかえれば”日に新た”でなくてはならない。この社会はあらゆる面で絶えず変化し、移り変わっていく。
だから、その中で発展していくには、企業も社会の変化に適応し、むしろ一歩先んじていかなくてはならない。
(本文中より)
時代とともに人間が進化してきたのと同じく、企業活動もその歩みを止めることなくその時代にあわせ進化し変化していくことが至上命題といえます。
安きに付けば、現状維持に甘んじて組織は弱体化します。
歴史ある企業ほど過去の成功体験にこだわるうちに、気がつけば今の時代にそぐわなくなっていて経営が行き詰まるといったケースもあるようです。
時を追うごとに変化のスピードは増していて、商品やサービスの消費スピードも加速し、時代背景によって、人の思考や価値観も常に変化しています。
常に時代を読み、その時々の需要を敏感に察知して、期待に応えるべく価値ある商品やサービスをを供給して、適正な利益を報酬として受け取る活動にこそ、時代に合う価値があるのだと考えます。
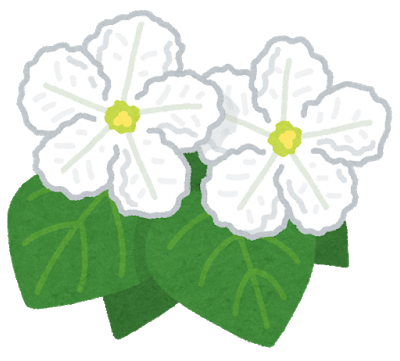
本書を読み終えて kou’s書籍レビュー
松下幸之助の実践する経営哲学の中心には、常に人が幸せになるための理念があるように考えます。
企業は、価値ある商品やサービスをを供給することで経済を活性し、その対価として得た利益報酬により、そこにたずさわる従業員の物心ともに豊かにしていくところに社会貢献としての役目もあるのだと考えます。
変化の激しさを増す現代にあって、人の持つ価値観もめまぐるしく変わっています。
価値観の変化とともに、求められる商品やサービスにも変化があって当然ですし、供給する企業側にも社会の公器としての役割を果たしつつ、時代に合わせる変化をも求められています。
そうしたお互いに切磋琢磨しあう関係性のなかにこそ、松下幸之助の言う生成発展の道があるのだと考えます。
企業も、商品も、サービスも、すべては人の活動であり、人が創出するものである以上、すべての人が物心ともに豊かになるための活動こそが経営といえるのではないでしょうか。
すべての人が個々の持つ能力や個性を存分に発揮しつつ、新たな価値を創出できる企業や環境こそが、次世代においても必要とされ、存続発展できるのだと考えます。

★この記事を書いた人★
 kou&バニ
kou&バニ
「本」こそが人生の師「KOU」と「バニ」です!
本を読み、先人の知恵や思考・生き方に触れることは、現代人にとっても良き人生をつむぐためのエッセンスとなりえます。
これまでも読書をするなかでは、多くの気づきと勇気を授かりました。
その数多くの「気づき」のひとつひとつは、血となり肉となり生き方を変えます。
書籍をもとに、人生をより良く変える思考を読み解きます。
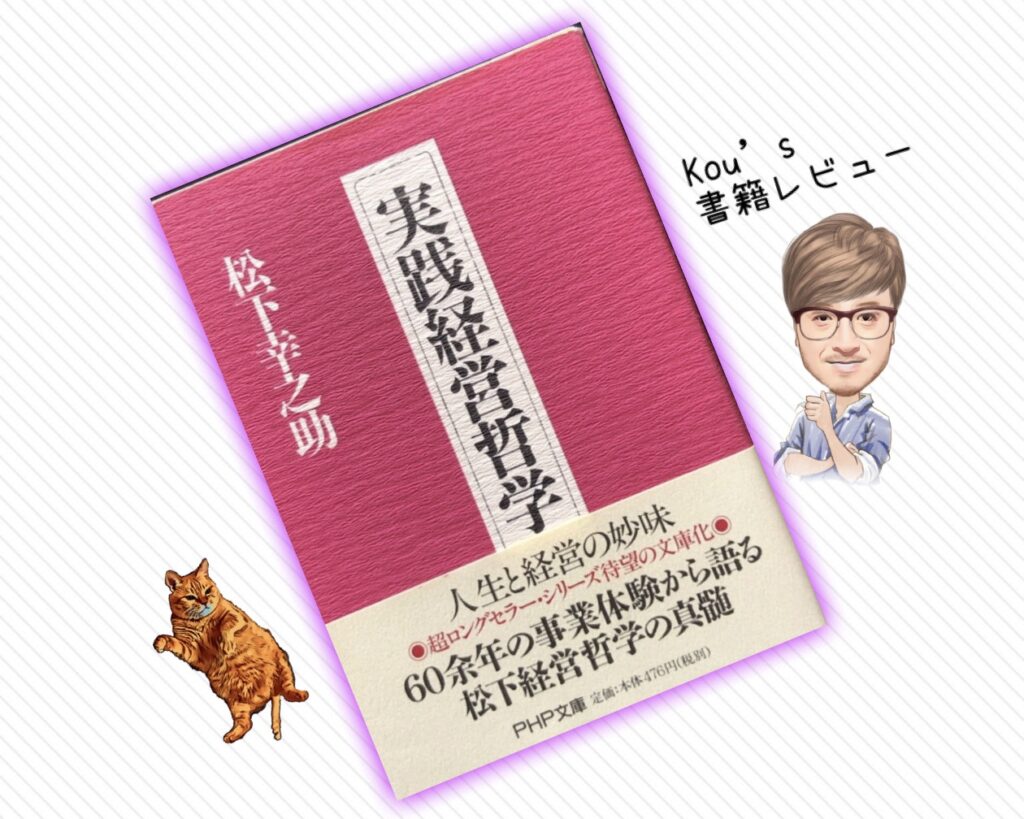


コメント